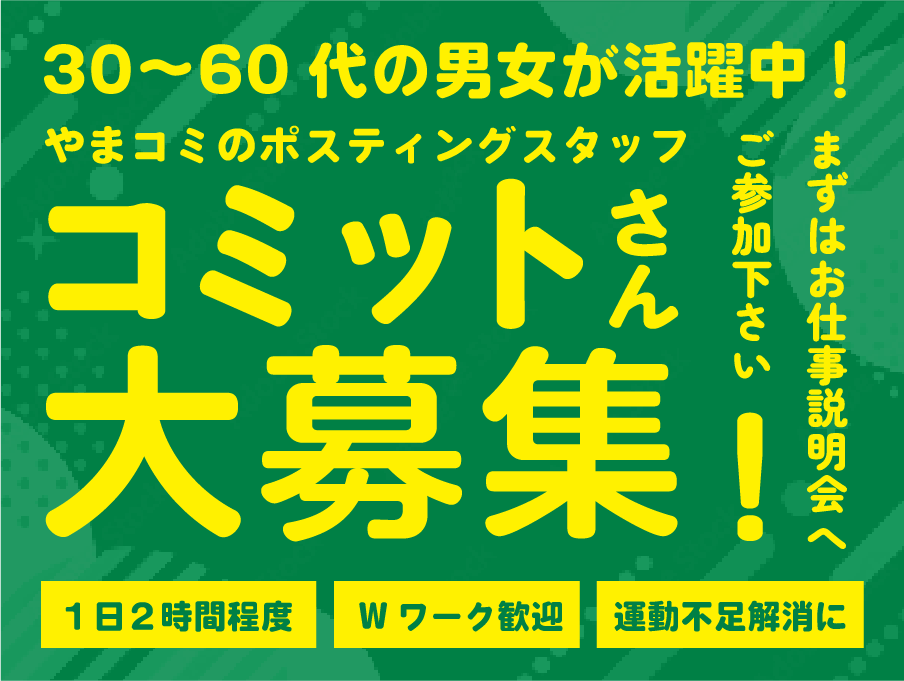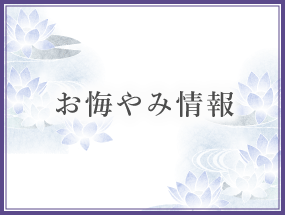源 義経:第6回
浄瑠璃姫と一夜の契り
今回は義経伝説を彩る女性を紹介しよう。名を「浄瑠璃姫(じょうるりひめ)」という。室町時代に成立した「浄瑠璃物語」(「十二段草子」とも)に登場する。
「瑠璃」は仏教語でアフガニスタンで取れる宝石「ラピスラズリ」のことで、「浄」は清らかな瑠璃のように美しい姫の姿の形容である。むろん架空のキャラクターだ。

義経がまだ牛若丸と名乗っていた少年時代、黄金商人の金売吉次(かねうり きちじ)に誘われて従者となり、京の鞍馬山を出て奥州平泉に向かった。途中、三河国矢作(やはぎ)(現在の愛知県岡崎市)で土地の長者の娘で当時14歳の浄瑠璃姫と出会い、素性を明かさないまま一夜を契(ちぎ)った。
浄瑠璃姫は長者が峯薬師(みねのやくし)に願って授かった申し子だった。峯薬師とは現在の愛知県新城市にある鳳来寺の通称で、日向薬師(ひなたやくし)(神奈川県伊勢原市)、柴折薬師(しばおれやくし)(高知県大豊町)と並ぶ日本三薬師の一つに数えられ、子授けのご利益で知られている。
牛若はその後も旅を続けるが、駿河国蒲原(かんばら)(現在の静岡市)で重い病に倒れ、吹上(ふきあげ)の浜に捨てられてしまう。
浄瑠璃姫は正八幡大菩薩のお告げで牛若の危機を知り、吹上浜に駆けつけて祈りで義経を蘇生させる。牛若は再会を約して浄瑠璃姫を天狗に送らせて矢作に帰し、自身は平泉に向かっていく。
この話は室町時代に成立し、峯薬師に参拝を勧める子授け霊験話と義経伝説とが複合して各地に広まっていった。尼の姿で各地を放浪した女性の芸人「歌比丘尼(うたびくに)」「念仏比丘尼(ねんぶつびくに)」たちが中心となって語り広められた。
やがて琵琶(びわ)の伴奏で語られる芸能として、他の演目も取り込んで発展していく。それらの語り物は原型である物語のヒロインの名を取り「浄瑠璃」と総称されるようになった。
江戸時代になると三味線が琵琶に取って代わり、操り人形と合体して「人形浄瑠璃」として発展、現在に至っている。
高校時代に文学史でこの芸能のことを初めて教わったのだが、「漢字が複雑だし、発音も舌をかみそうだな」という印象を持った程度で、当時は義経の思い人の名前に由来するなどとはまったく想像しなかった。

山大学術研究院教授
山本 陽史(やまもと はるふみ)
和歌山市出身。山大学術研究院教授、東大生産技術研究所リサーチ・フェロー、日本世間学会代表幹事。専攻は日本文学・文化論。著書に「山東京伝」「江戸見立本の研究」「東北から見える日本」「なせば成る! 探究学習」など多数。米沢市在住。